排尿日誌
📝 排尿日誌とは?〜排尿の記録から見える体のサイン〜
排尿日誌(排尿記録)は、毎日の排尿状況を客観的に把握するための記録シートです。
頻尿、尿漏れ、夜間のトイレ、残尿感などの症状がある方にとって、症状の原因を探る大切な手がかりとなります。
例えば「どの時間帯に頻尿が多いのか?」「水分摂取との関係は?」「夜間の排尿は何回?」といった情報が明らかになり、診察時により的確な診断・治療方針の決定に役立ちます。
💡 3日間ほど記録するだけでも、症状のパターンや生活習慣との関連が見えてきます。
ご自身の身体のサインを見逃さないために、排尿日誌を活用してみましょう。
🧾 排尿日誌をつけるのに必要なもの
排尿日誌を正確かつ無理なく記録するために、以下の準備物があると便利です。
特別な道具は不要ですが、記録を続けるための工夫が大切です。
- ✅ 記録用紙またはアプリ
… 紙のシート、スマホメモ、表計算ソフトなど、お好きな方法でOK。 - ✅ 時計やスマートフォン
… 排尿や水分摂取の正確な時刻を記録するために必要です。 - ✅ 軽量カップ
… 目安としてコップ1杯=約200ml程度で記録できれば十分です。 - ✅ 筆記用具
… 紙で記録する場合に使います。ボールペンやシャープペンでOK。 - ✅ 水分摂取の意識
… 飲んだものの種類・量・時間も一緒に記録すると診断の助けになります。 - ✅ 3日間続けるモチベーション
… 平日と休日での排尿パターンの違いも重要な情報になります。
💡 記録はざっくりでも大丈夫です。完璧を目指さず、まずは続けてみることが一番のポイントです。
📄 排尿日誌テンプレートと記入例
自宅で排尿の状態を把握するために、排尿日誌の記録がとても役立ちます。
以下のリンク先に、印刷して使える排尿記録表(白紙)と記入例が用意されています。
まずはそちらをダウンロード・印刷してお使いください。
👉 印刷用PDFはこちらから:
https://www.yakan-hinnyo.com/chart/chart03.php
■ 白紙テンプレートについて
シンプルな表形式で、時刻・排尿量・尿意の強さ・水分摂取量などを記録できます。
スマホで記録しても、紙に手書きでも大丈夫です。
■ 記入例について
実際の記録例が掲載されており、どう書けばいいかの参考になります。
迷ったら「記入例」を見ながら始めてみましょう。
| 時刻 | 排尿量 | 尿意の強さ | 水分摂取量・内容 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 200ml | 強い | 水200ml(朝食) | 起床後 |
| 10:00 | 150ml | 中 | お茶150ml | 仕事中 |
| 13:00 | 180ml | 強い | 水300ml(昼食) | 外出先 |
💡 このように、何時に・どれくらい・どんな症状だったかをメモするだけで、医師の診断に大きく役立ちます。
📚 排尿日誌に関する参考文献とエビデンス
排尿日誌(排尿記録表)は、排尿障害や頻尿・尿失禁の評価に有効なツールです。
以下に、医療専門家・公的機関・学会ガイドライン・国際的な臨床情報サイトからの信頼性の高い情報源をご紹介します。
- 夜間頻尿.jp|排尿記録表テンプレートと記入例
- 日本泌尿器科学会|排尿障害の診療指針
- 厚生労働省|高齢者の排尿自立支援に関する手引き
- Minds|過活動膀胱診療ガイドライン(日本排尿機能学会)
- 日本老年医学会|高齢者泌尿器疾患のガイドライン
- Urology Care Foundation(米国泌尿器科学会)|OABと排尿日誌
- NHS(英国国民保健サービス)|尿失禁と記録の重要性
- AUA(米国泌尿器科学会)|診療ガイドライン集
- PubMed Central|排尿日誌に関する論文検索
- UpToDate|Voiding Diary(排尿日誌)の解説(要ログイン)
- Medscape|排尿障害の診断と記録方法
👨⚕️ 医師からのコメント・監修
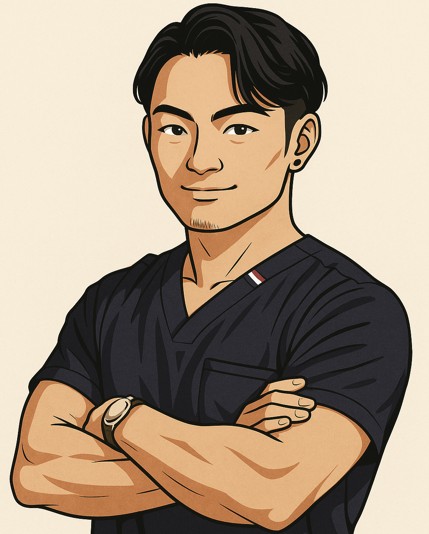
「排尿日誌は、日常の排尿状態を客観的に把握できる貴重な情報源です。
特に夜間頻尿や過活動膀胱、尿失禁の診断・治療方針を立てる上で、非常に有用なツールとなります。」
私たちは、問診だけではわかりにくい排尿パターンや水分摂取の影響を、排尿記録から丁寧に読み取り、患者さま一人ひとりに適した診療を提供しています。
恥ずかしがらず、ぜひご自身の状態を知る第一歩としてご活用ください。
0th CLINIC
・日本泌尿器科学会認定 泌尿器科専門医
・日本抗加齢医学会専門医
・テストステロン治療認定医

「記録から見える排尿のリズムや変化は、医師が原因を絞り込む大きな手がかりになります。
どのタイミングで、どのくらい出るのかという情報は、単なる感覚よりずっと正確です。」
排尿日誌は、医師と患者が同じ視点で症状を共有するための“架け橋”です。
生活習
関連コラム
ただいま準備中です。少々お待ちください。
