粉瘤の病理検査で何がわかる?悪性との違い

粉瘤の病理検査で何がわかる?悪性との違い
粉瘤(ふんりゅう/アテローム)は皮膚の下にできる袋状のしこりで、標準的には局所麻酔で被膜ごと切除します。 その際、必要に応じて病理検査(顕微鏡診断)に提出し、「本当に粉瘤か」「似た病気が紛れていないか」「炎症/破裂の影響」を確認します。
- 病理は診断の最終確認と類似疾患の除外に役立ちます。
- 急速増大・再発・非典型などは病理提出を積極的に検討します。
- 再発予防の基本は嚢腫壁(被膜)を残さず切除することです。
対話で整理:あなたの状況はどれ?(病理が必要かの目安)
「結局、私は病理に出した方がいい?」を、よくある状況別に対話形式で整理します。
Q1:見た目が典型的な粉瘤なら、病理は不要ですか?
切除はしたいけど、病理は毎回必要なのか迷っています。
A:
典型的な粉瘤では必須でない場合もあります。ただし、診断の確証が欲しい、部位が重要、再発、急速増大などがある場合は、 病理提出のメリットが大きくなります(下のチェックも参考にしてください)。
Q2:急に大きくなりました。悪性が心配です。
最近、短期間でサイズが変わった気がします。
A:
急速増大は「炎症/破裂で腫れる」ことでも起こりますが、非典型経過として病理提出を検討しやすい状況です。 触診・必要に応じて超音波で状態を確認し、切除標本を病理へ提出して粉瘤以外の疾患が紛れていないかも含めて評価します。
Q3:何度も腫れて破れて、再発しています。
切ってもまた同じところが腫れます。
A:
反復炎症では周囲が瘢痕化し、被膜の扱いが難しくなることがあります。病理は「炎症/破裂の影響」を読み解き、 その後の説明や方針(時期・術式)に役立ちます。再発予防の基本は被膜ごとの切除です。
チェック:病理提出を検討しやすいケース
※チェックが多いほど「病理提出のメリット」が増える傾向があります。最終判断は診察で行います。
病理検査で「具体的に」わかること
- 診断の確定:粉瘤(表皮嚢腫)か、類似疾患(脂肪腫、皮様嚢腫、毛包嚢腫〈トリキレーマ嚢腫〉、ステアトシストーマ等)かを判定。
- 炎症・破裂の影響:嚢腫破裂や肉芽組織形成、炎症の程度などを評価。
- 見落とし防止:粉瘤に似る別疾患・腫瘍を除外(必要に応じ追加評価)。
- 説明の質が上がる:「なぜ腫れたのか」「今後どうするか」を病理所見と臨床所見で噛み砕いて説明できます。
※病理所見は標本の部位・状態(破裂の有無など)で解釈が変わります。診察所見(大きさ・経過・部位)と合わせて総合判断します。
良性と悪性の違い(病理学的視点の概要)
| 項目 | 良性(粉瘤など) | 悪性が疑われる場合の所見(例) |
|---|---|---|
| 基本構造 | 角化を伴う嚢腫壁(表皮様上皮)+内容物(角質) | 浸潤性増殖、構造の乱れ、壊死を伴う不規則な増殖 |
| 細胞の性状 | 細胞異型は軽微〜なし | 核異型・核分裂像増加、角化傾向の異常など |
| 周囲組織 | 破裂に伴う炎症・肉芽形成は起こり得る | 神経/血管/脂肪層への明らかな浸潤、破壊性増殖 |
| 臨床経過 | ゆっくり増大、炎症時に腫脹・疼痛 | 急速増大、潰瘍化、止血困難、強い固定感など(臨床で要注意) |
※上記は概略です。実際は「臨床像(速度・部位・再発)+画像(必要時)+病理」で判断します。
どんな時に病理検査を検討する?
- 典型像から外れる、または急速に大きくなっている
- 繰り返す感染・破裂で瘢痕や癒着が強い
- 顔面・外陰部・手指など重要部位で再発/非典型経過
- 視診・触診・超音波などで他疾患が疑われる(脂肪腫、血管性病変など)
- 患者さまが診断の確証を希望される
当院では切除標本を適切に処理し、連携先で病理診断を行います。結果は後日、わかりやすくご説明します。
よくある質問(病理と悪性鑑別)
粉瘤は必ず病理検査が必要ですか?
典型的な粉瘤では必須でない場合もありますが、非典型・急速増大・再発・重要部位・他疾患が疑われる場合などは提出を検討します。最終判断は診察で行います。
悪性の粉瘤はありますか?
粉瘤そのものが悪性化することは一般に稀とされますが、粉瘤に似た腫瘍が紛れる可能性はゼロではありません。臨床像と病理所見を合わせて鑑別します。
病理結果はいつわかりますか?
通常は数日〜2週間程度で結果説明が可能です(病理機関や追加染色の有無で前後します)。
再発を防ぐには?
再発予防の基本は嚢腫壁(被膜)を残さず切除することです。炎症が強い場合は、切開排膿で落ち着かせてから根治切除を計画することがあります。
監修・クリニック情報(信頼型構造)
医師からのコメント・監修

「粉瘤は“よくあるしこり”ですが、再発や非典型例では見立てが重要です。必要な時に病理で最終確認することで、安心と納得につながります。」
監修:黒田 揮志夫 医師(病理専門医/消化器病理医)
0th CLINIC 日本橋 院長/医学博士
日本病理学会認定 病理専門医/プライマリ・ケア連合学会認定 プライマリ・ケア認定医
日本医師会認定 産業医/健康スポーツ医/総合診療・救急科での診療歴10年以上
連携医師(専門領域のバックアップ)
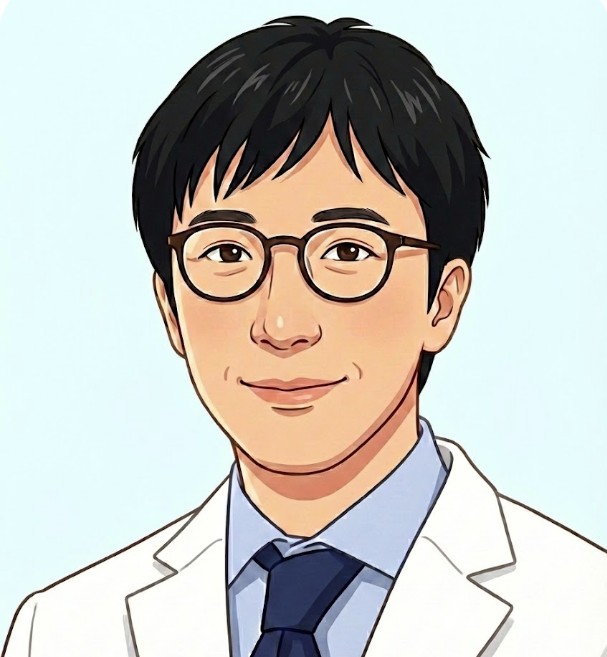
遠藤 大介 医師(成人心臓血管外科)
筑波大学医学専門学群医学類(2010年)/順天堂大学大学院(2017年)
日本外科学会 外科専門医/三学会構成 心臓血管外科専門医・修練指導者/腹部・胸部ステントグラフト実施医・指導医/TAVR/TAVI 実施医/ロボット支援下心臓手術認定術者
※皮膚科の粉瘤診療は皮膚科の診察にて行います。基礎疾患(抗凝固薬内服など)や全身管理が必要な場合に、連携体制が安心材料になります。
0th CLINIC 日本橋 アクセス情報
〒103-0027
東京都中央区日本橋2丁目16番9号 CAMCO日本橋ビル4F
※1F入口で部屋番号「401」を押してお入りください。
■ 日本橋駅 徒歩3分
東京メトロ銀座線・東西線、都営地下鉄浅草線「D1出口」
■ 茅場町駅 徒歩5分
東京メトロ日比谷線「12番出口」
※お車でお越しの場合は、近隣のコインパーキング等をご利用ください。

地図
東京都中央区日本橋二丁目16番9号 CAMCO日本橋ビル4階(東京駅八重洲口・日本橋駅から徒歩3分)
診療時間(現在)
| 曜日 | 時間 | 備考 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00–20:00 | — |
| 火 | 11:00–20:00 | — |
| 水 | 9:00–17:00 | — |
| 木 | 9:00–17:00 | — |
| 金 | 9:00–20:00 | — |
| 土 | 9:00–14:00 | — |
| 日・祝 | 休診 | 現在 日・祝は休診 |
※ 発熱外来は予約制・承認制でのご案内です。必ずLINEからご予約ください。
※本コラムは一般的な情報提供です。診断・治療の可否や手術時期は、診察のうえ医師が個別に判断します。 急速な腫脹・強い疼痛・発熱・持続する出血などがある場合は、早めに医療機関へご相談ください。

