2型糖尿病
最も多いタイプ。体重・腎機能・低血糖リスクも踏まえて個別化します。
「健診で高いと言われた」「境界型/予備群かも」「すでに糖尿病で薬や管理を見直したい」—— まずはいまの状況から最短で整理します。責めないだけで終わらせず、合併症を防ぐ設計と見える化(CGM/TIR)を大切にしています。
最短は再検(採血)+背景チェックをまとめて行うこと。予備群の段階で“続く形”を作るほど、その後がラクになります。
脱水で血糖が悪化しやすく、薬の調整が必要なことがあります。水分が取れない、嘔吐が続く、息が深い/速い、意識がぼんやりは要注意。
“数値だけ”ではなく、生活の現実に合わせて最適化。必要なら早期から効果的な薬やデバイスも検討し、合併症を防ぐ設計へ。
症状がある高血糖は放置しない方が安全です。早めに受診をご検討ください。
検索で多い「糖尿病 食べてはいけないもの」は、禁止リストを作っても長続きしないことが多いです。 大事なのは 頻度・量・順番・組み合わせ。外食中心の方は“テンプレ化”が効きます。
完全禁止より、頻度と同日の他の食事、歩く/運動で調整。 「いつ・どのくらい・何と一緒に」を決めるとブレが減ります。
短期では下がっても、反動で崩れることがあります。続く配分(量の設計)が最短です。
選び方の型で改善できます。朝/昼/夜の固定テンプレを作ると継続しやすいです。
「糖尿病かどうか」だけでなく、合併症リスクと治療選択の条件(腎機能など)を同時に整理すると、遠回りしません。 詳細は 検査ハブ へ。
最も多いタイプ。体重・腎機能・低血糖リスクも踏まえて個別化します。
インスリンが必要。CGMや生活設計でQOLの底上げを狙います。
母児の安全が最優先。必要に応じて診療連携・栄養設計を行います。
数値だけでなく、低血糖回避、体重、睡眠、仕事との両立まで含めて“現実解”の目標へ。
生活+薬+デバイスを組み合わせ。腎機能や体重、リスクを見て個別化します。
CGM/TIRなど“見える化”で、ブレの原因を一緒に特定し、続く形へ。
※本ページは一般的情報です。最適な治療は、合併症・腎機能・併用薬などで変わります。
しびれや小さな傷の治りにくさは、神経・血流・感染の複合で起きます。 「小さいうちに評価」が安全です。気になる場合は早めにご相談ください。
最短は、再検(採血)で数値を確認しつつ、腎機能・尿検査・脂質など背景も同日に整理することです。 予備群の段階で“続く形”を作ると、後から楽になります。健診→再検の流れへ。
禁止リストは続きにくいことが多いです。頻度・量・組み合わせ(同日の他の食事)で設計し、長期で勝てる形を作りましょう(食事セクション)。
脱水で血糖が悪化しやすく、薬の調整が必要なことがあります。 水分が取れない、嘔吐が続く、息が深い/速い、意識がぼんやり等は要注意。シックデイ、DKAもご確認ください。
まずは“最短で整理”し、その後は無理のない頻度に設計します。通院中断が一番リスクなので、生活背景も含めてご相談ください。
〒103-0027
東京都中央区日本橋2丁目16番9号 CAMCO日本橋ビル4F
※1F入口で部屋番号「401」を押してお入りください。
■ 日本橋駅 徒歩3分
東京メトロ銀座線・東西線、都営浅草線「D1出口」
■ 茅場町駅 徒歩5分
東京メトロ日比谷線「12番出口」
※お車でお越しの場合は、近隣のコインパーキング等をご利用ください。

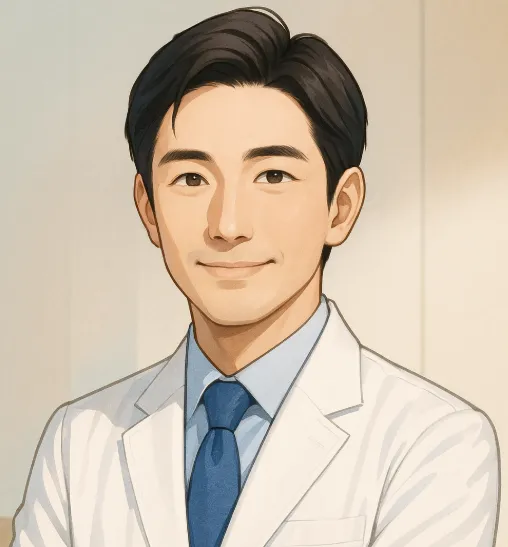
「数値だけでなく、患者さんの“今”に寄り添いながら、合併症を防ぐための現実的な設計を一緒に作ります。」
当院では、検査の“抜け”を減らし、必要な治療を必要なタイミングで行うことを重視しています。 迷ったら、まずは健診結果を持ってご相談ください。
ただいま準備中です。少々お待ちください。