目的
- LDL低下と心血管イベント予防(心筋梗塞・脳卒中など)
- 非HDL・ApoBの改善にも寄与(残余リスクの評価にも)
結論:スタチンはLDLを下げて心筋梗塞・脳卒中を予防する大切な薬です。
ただし筋肉痛(SAMS)や相互作用が絡むと「続けられない」ことも。0th CLINICでは
原因整理 → 安全確認(CK/腎/肝など)→ 続く処方へ再設計を一緒に行います。
(日本橋駅3分/24時間LINE予約)
※ 強い筋痛・脱力・発熱・茶色い尿(赤褐色尿)がある場合は至急受診をご検討ください。
※ 妊娠・授乳中は原則使用しません。妊娠希望がある場合は早めにご相談ください。
| 薬剤 | 一般的な強さ(LDL低下) | 服用タイミング | 補足 |
|---|---|---|---|
| ロスバスタチン(クレストール®) | 強い(高強度まで可) | いつでも(1日1回) | 腎機能に応じ用量調整 |
| アトルバスタチン(リピトール®) | 強い(高強度まで可) | いつでも(1日1回) | CYP3A4相互作用に注意 |
| ピタバスタチン(リバロ®) | 中〜やや強め | いつでも(1日1回) | 相互作用が比較的少なめ |
| シンバスタチン(リポバス®) | 中等度 | 就寝前が一般的 | CYP3A4相互作用に注意 |
| フルバスタチン(ローコール®) | やや弱め | 就寝前が一般的 | 相互作用は比較的少なめ |
※ 表は目安です。個別の目標・併用薬・体質で最適解は変わります。
→ 継続する場合は自己判断で中断せずご相談を。
→ この場合は至急受診。CK・腎機能評価とお薬調整が必要です。
※ 独断での中止・再開は避け、必ずご相談ください(再挑戦は別系統/低用量/隔日や非スタチン併用で調整)。
| カテゴリ | 代表例 | ポイント |
|---|---|---|
| CYP3A4阻害 | マクロライド系、アゾール系、グレープフルーツ | 特にシンバ/アトルバで血中濃度↑ → 筋症リスク |
| OATP1B1阻害 | シクロスポリン等 | 肝取り込み↓で曝露↑ → 用量調整や他剤へ |
| フィブラート併用 | フェノ/ペマ/ベザ 等 | ベネフィット>リスクの時に慎重併用(CK/LFT観察) ※ ジェムフィブロジルは併用回避が一般的 |
| その他 | 抗凝固薬、免疫抑制薬、抗不整脈薬など | 相互作用・出血/筋症リスクを個別に評価 |
※ サプリ・健康食品も必ず共有してください(赤酵母米など)。

「“効かせる工夫”と“安全に続ける工夫”は両輪です。症状・検査・内服歴を統合し、無理なく続く処方に仕立てます。」
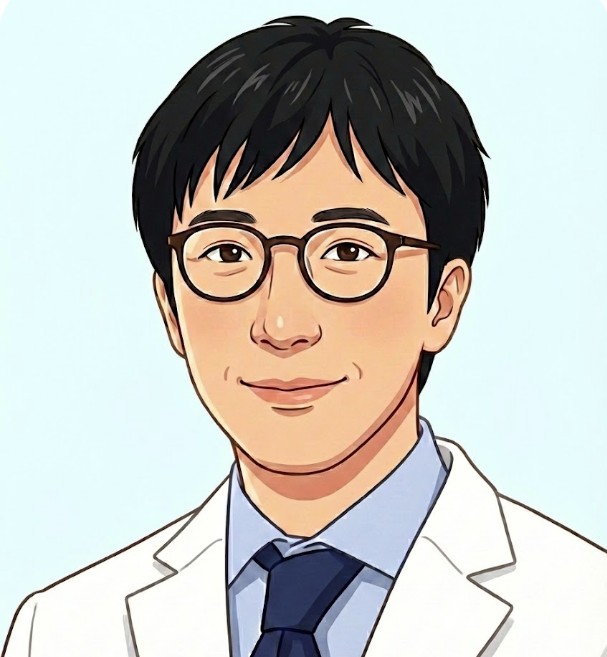
心血管イベント予防の観点から、脂質管理(LDL目標設定・治療強度)を臨床的に整理して監修します。
※ 本ページは一般的な情報提供であり、診断・治療は個別の状態で変わります。症状が強い場合は早めにご相談ください。
〒103-0027
東京都中央区日本橋2丁目16番9号 CAMCO日本橋ビル4F
※1F入口で部屋番号「401」を押してお入りください。
■ 日本橋駅 徒歩3分
東京メトロ銀座線・東西線、都営地下鉄浅草線「D1出口」
■ 茅場町駅 徒歩5分
東京メトロ日比谷線「12番出口」
※お車でお越しの場合は、近隣のコインパーキング等をご利用ください。

ただいま準備中です。少々お待ちください。